| 沿革 |
1953年 - GHQによって禁止されていた薙刀術復活のための委員会設置
1954年 - 指導教材作成委員会設置
1955年 - 全日本剣道連盟から独立。全日本薙刀(なぎなた)連盟発足
1968年 - 財団法人化
1978年 - 日本体育協会に加盟
1991年 - 国際なぎなた連盟に加盟
2013年 - 公益財団法人化
|
| 第二次世界大戦による敗戦(1945年)のため一時禁止されていた武道が1953年ようやく復活し、1955年に全日本なぎなた連盟が新しい武道として発足しました。各県の連盟からなるこの組織は45万の会員を擁しこのうち6万4千人が資格を持っています。現在では中学、高校のクラブにも採用され会員は徐々に増えています。毎年全日本選手権大会ほか各種大会が催され又、国体、インターハイにも参加しています。 国際的には1990年に国際なぎなた連盟が発足し、現在はベルギー、ブラジル、フランス、オランダ、ニュージーランド、スウェーデン、アメリカ、チェコ、オーストラリア日本の14ヵ国が加盟しています。外国では男子に人気があり、様々な交流を通して普及を計っています。4年に一度の割合で世界大会も行われています。アセアン諸国にはなぎなたが取り入れられていませんので理解と協力を得たいと努力しているところです。 |
| 設立以来の主な活動実績 |
日本のなぎなた界を統轄し、代表する団体として、なぎなたの修錬により、心身ともに調和のとれた人材を育成するという理念を掲げて、広く国民の間になぎなたの普及振興を図るとともに、国際なぎなた連盟に加盟し、国際交流を推進している。
全日本なぎなた選手権大会、全日本男子なぎなた選手権大会、都道府県対抗なぎなた大会、全日本学生なぎなた選手権大会、全国中学生なぎなた大会等の開催、国民体育大会なぎなた競技会、全国高等学校総合体育大会なぎなた競技会,全国 高等学校なぎなた選抜大会への共催・参加、そして生涯スポーツとしてのエンジョイなぎなた全国大会の開催などを通じて、なぎなた人口の増加を図っている。
また、世界なぎなた選手権大会を4年ごとに開催することとし、その中核的役割を果たしている。
一方、なぎなたの普及振興のため指導者の養成は緊要であり、多角的な視点で多様な講習会・研修会を実施し、海外からの要請にも対応している |
| 団体の目的 |
日本のなぎなた界を統轄し代表する団体として、広く国民の間になぎなたの普及振興を図り、もって明朗優雅にして強健な青少年の育成に寄与する事を目的とする。
業務
(1)なぎなたの普及、啓蒙および指導
(2)なぎなたに関する調査および研究
(3)なぎなたの競技大会、講習会および講演会等の開催および後援
(4)なぎなた指導者の養成および資格付与
(5)加盟団体の助成および指導
(6)なぎなたの称号および段位の授与
(7)功労者の表彰
(8)なぎなたの国際交流事業の推進
(9)なぎなたの施設および用具についての研究
(10)会報その他刊行物の発行
(11)その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
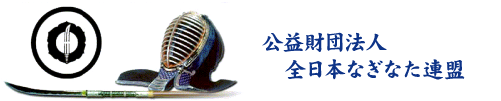
![]()
